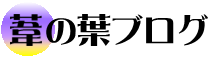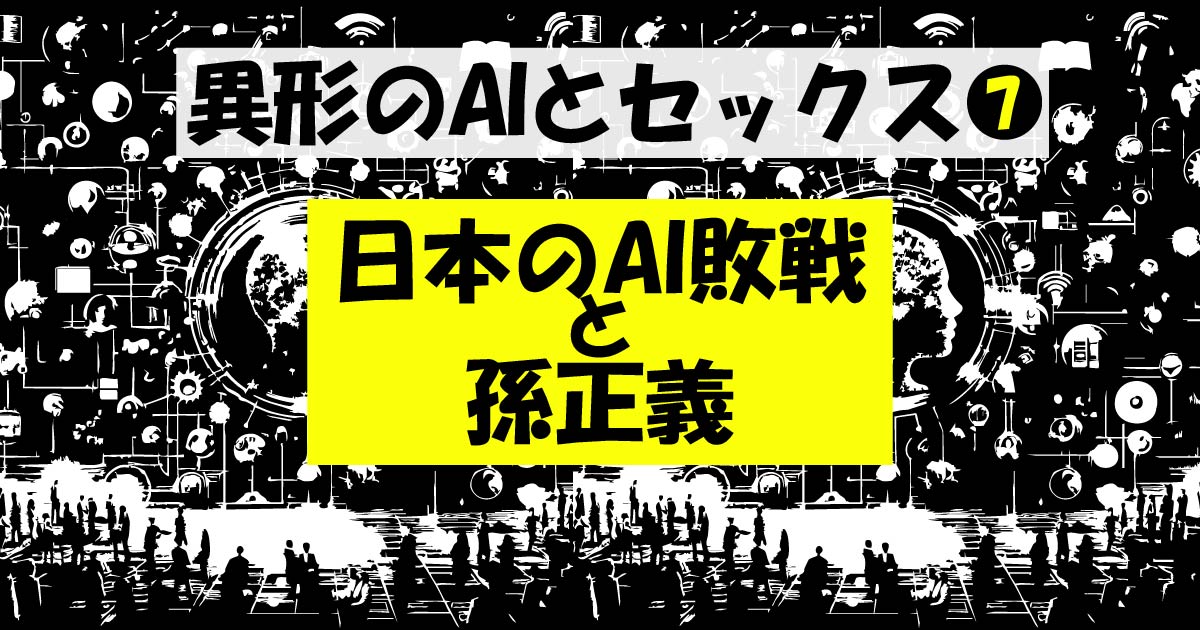6号で終了予定であった本連載を急遽延長して7号をお届けいたしますが、延長を決めた時点ではなかった新たな事態も加わりまして、当初予定していた内容とはかなり変わった展開となりました。その変更点は一言でいえば、本号のタイトルにもなった「日本のAI敗戦」にも孫正義が関与していたという事実を確認したということです。
1.OpenAI 01を大礼賛!
本連載は6号で終了する予定でしたが、異形のAIとセックス6「4.解散命令と孫正義」に追記しましたように、孫正義とOpenAIのサム・アルトマン氏とが日本で新会社を設立するとのニュースが入りましたので、連載7号としてこの新たな展開について書くことにしました。
この追記では、中国のDeepSeekの登場後はOpenAIのChatGPTは2流になったと指摘しましておりましたが、なんとその数日後の4/6付け西日本新聞に、ライフプロンプト(LifePrompt)が実施したという、東大の二次試験問題を使った、DeepSeekとChatGPT 01(オーワン・ChatGPT4の進化形)の能力対比記事が出ていました。他紙でも報道されているようですので、全国で報道されたものと思われます。結果は、もちろん01の圧勝。
しかも西日本新聞には、イタリアでは、ChatGPTを使って全記事を作成した新聞が発行されているという記事まで並べられており、最新の01はもとより、ChatGPTも非常に優れた生成AIとして国内外で評価されていることを実例で示す記事がドーンと目立つ場所に掲載されていました。
明らかに、わたしの孫正義批判追記に対する嫌がらせですね。わたしの孫正義批判ブログのせいなのか、今年のソフトバンクホークスは開幕から連敗続きで最下位。地元紙としては、この異例の連敗は、わたしの孫批判が影響していると判断したのかもしれません。
それならば、孫と統一教会とがわたしの頭脳をタダで利用しているだけではなく、孫と統一教会の手下が我が家に侵入して、個人情報(親族リスト+戸籍情報等の詳細情報)や貴重な資料(セックスツールの悪魔的側面を記載した文書)に加え、現金70万円余りも盗んだというわたしの被害も報道していただきたいと思いますが、わたしの被害は完全無視。
西日本新聞はOpenAIの礼賛記事に加え、見開き左のページには、2018年7月に死刑が執行された、オウム真理教の信者であった息子の母親へのインタビュー記事が、紙面を覆うほどの大きさで掲載されていました。
オウム真理教事件から30年の節目の年。加えて入学シーズンですので、カルト教団への注意を促す記事の掲載は意義があるとはいえ、右にOpenAIの礼賛記事、左にオウム真理教の凶悪事件を思い起こさせる記事。とても偶然だとは思えません。
西日本新聞は、公正さを旨とする報道機関なのかとの疑問を禁じえませんが、この記事が功を奏したのか、ソフトバンクホークスは久々に勝利、連敗を脱しました。その後も勝利が続いているようですが、公正さをかなぐり捨てたような記事で応援して手にした勝利は、本当に勝利だといえるのか。勝ったとしても非常に後味の悪い勝利です。
そもそもOpenAIの01とDeepSeekとの比較そのものが非常に公正さを欠いた記事だったのですが、不思議なことに、01の性能礼賛記事は出ていても、批判、批評などは今のところ皆無です。
なお、孫正義がなぜわたしの頭脳をタダで利用し、70万円余りの自宅にあった現金まで盗ませたのかといえば、セックスツール開発、拡販にわたしが協力したという証拠を残さないためです。孫一人の手柄にするためです。
現金の窃盗は、窃盗に入った孫と統一教会の手下への文字通りの駄賃。窃盗を実行させるためのモチベーションを高めるためのインセンティブの役目も負っていたはず。加えて、もともと貧しいわたしをさらに貧窮に追い込み、窃盗集団の奴隷にまで成り下がるか、ブログ発信どころか、生存すら諦めざるをえない状況に追い込むことを狙ったもの。
同じ論理で、このツールを開発した日本人技術者は、消されたのではないかと想像しています。発明者が今も存命ならば、孫一人の独壇場にはなっていないはずだからです。
このツールを世に知らしめたのは、わたしのブログが唯一の広報源ですが、今も顧客が引きも切らずに訪れているという。孫はあくどい手法で金儲けを続けているわけです。
2.ChatGPT対DeepSeek
続いて本題に入ります。
01の高性能さを華々しく証明したライフプロンプトは、2,023年5月に設立されたAIベンチャーですが、4/12に確認した段階では、実績一覧ライフプロンプト 事例・実績には6例表示はされているものの、具体的な紹介がなされているのは、「【ついに9割!】共通テスト2025をChatGPTに解かせてみた」という大学入試の共通テストに関するプロジェクト一例のみ。この一例以外では具体的な紹介はなく、「準備中」との表示になっています。
同社は23年5月創業という若い会社ですので、実績はまだ少ないとしても無理からぬこととは思いますが、一覧には6例を表示していながら中身がないというのは、いささか誠実さに欠けるのではないかとも思います。
唯一具体的な紹介のある実績からすると、同社は日本の大学入試問題を生成AIに解答させるという仕事を中心に事業をスタートさせたらしいことが分かります。23年と24年は、ChatGPTに共通テストを解かせた結果が、同社のnoteサイトに紹介されています。
【2024年1月最新】共通テストを色んな生成AIに解かせてみた(ChatGPT vs Bard vs Claude2)
株式会社LifePrompt 2024年1月16
【2023年入試】ChatGPTに共通テスト(旧センター試験)を解かせてみた
株式会社LifePrompt
2023年6月9日
上記報告を見ると、ChatGPTの「賢さ」がダントツであることが分かります。翌年、日経新聞がライフプロンプトに提携を申し入れて、AIを使って東大入試に挑戦しました。以下は、そのプロジェクトを報告した連載4回の記事です。会員限定記事で非公開ですが、タイトルから概略は推測できるかと思います。
①ChatGPTは東大に受かるか 旧センター試験得点率は67%
AI、東大入試に挑む①
2024年5月3日 日経新聞 [会員限定記事・・・以下同]
この1回目の記事はわたしも全文読んだのですが、初めの頃はChatGPTも苦戦したらしい。非公開記事を引用するのは違反かもしれませんが、ご容赦ください。
東大の2次試験は難易度が高く、合格に必要な得点率は例年5〜6割だ。得意の英語で貯金をつくり、国語や世界史の論述でその弁才を発揮し、やや苦手な数学の傷を抑えれば、東大に「合格」できるかもしれない。数学の配点が低い文系の方が、理系よりも望みがありそうだ。
しかし、皮算用が崩れるのは早かった。2月上旬、チャットGPTに東大2次試験の過去問を解かせたライフプロンプトから「文系でも4割しか得点できなかった」という報告が届いたためだ。受験本番まで残り3週間。合格レベルに達するまでAIを強化する「追い込み」が始まった。
とあるように、ChatGPTは、ここ2年余りの間に大学入試に特化した訓練が繰り返し行われてきただけではなく、東大入試問題に関する01の弱点を克服するような訓練も行われてきました。
②生成AIを「受験脳」に鍛える 本番で突如不機嫌に
AI、東大入試に挑む②
2024年5月4日 日経新聞
「2月上旬にチャットGPTに東大2次試験の過去問を解かせたところ、結果は自己採点で4割にとどまった。合格には最…(有料)」(記事冒頭部分)
③ 数学が1点では…ChatGPT、英語8割超も「東大不合格」
AI、東大入試に挑む③
2024年5月5日 日経新聞
「3月10日、記者は東京都内の大学キャンパスの一室で英語能力テスト「TOEIC」を受験していた。必死にマークシ… (有料)」(記事冒頭部分)
④ 東ロボくん、数学でChatGPTに勝っていた 読解力に差
AI、東大入試に挑む④
2024年5月6日 日経新聞
「うちの子もそうだった」
国立情報学研究所の新井紀子教授はインタビューの最中、東大不合格に終わったチャットG… (有料)」(記事冒頭部分)
そしてついに、グレードアップされた最新版ChatGPT01が東大入試を突破。
【東大理3合格】ChatGPT o1とDeepSeek R1に2025年度東大受験を解かせた結果と答案分析【採点協力:河合塾】
株式会社LifePrompt
2025年4月5日
この「偉業」は、基本的にそれまでのChatGPTとは飛躍的に性能が高度化した01の新たな到達度を示していると思われますが、01の性能の高度化には、ChatGPT4を使って、2年余りにわたって繰り返されてきた共通テストへのチャレンジ、東大入試への対応力を強化するための様々な対策、訓練がかなり貢献したはずです。
昨年5月の時点では最新のChatGPT4ですら数学は1点だったとのことですので、たった1年で合格点をはるかに超えるほどに性能アップ。人間では短期でここまでの飛躍は望めないと思いますので、生成AIの能力のすごさにはあらためて驚かされます。
ただ、今回問題にしたいのは、西日本新聞の記事から感じるあるバイアスについてです。ライフプロンプトが公開している結果からは感じない悪意に近いものです。
西日本新聞の記事だけを読んだ段階では、ChatGPT01がDeepSeekR1を圧倒しているとの印象が強く伝わってきます。特に、R1は理数系に強いといわれているにもかかわらず、教科別得点として紹介された文系数学では、R1は18点、対して01は40点。どちらも他の教科に比べるとかなり低いとはいえ、R1の18点は、その性能自体に大疑問符が付きそうなほどの低レベルです。
しかし、ライフプロンプトが公開している結果一覧を見ると、印象はかなり変わります。理系数学ではR1が49点、01が38点。R1が01をかなり上回っています、しかし西日本新聞は、この理系数学は紹介せずに、R1の得点が異常に低い文系数学だけを紹介したわけです。その意図はミヱミヱですね。
この文系数学も、ライフプロンプトの記事を読めば、正しい回答をしているが、回答の仕方に問題があったと、その低得点の理由が付されています。さらに、物理では、R1は高難度の解答もしたとの解説があり、理数系に強いというR1の基本性能は遺憾なく発揮されていたことが分かります。
しかも、01が前身のChatGPT4の時代から、繰り返し共通テストや東大の過去問を解く機会を与えられ、正答率を高めるための訓練を受けてきた結果、ChatGPTは01に至って飛躍的に性能を高めたという経緯を考えると、そういう東大入試の実訓練はほぼ皆無のR1が、総合点としては01とはさほど差異のない結果を残せたということは、むしろ、R1の性能の高さを証明しているのではないかとの評価もできるはずです。
もちろん、R1はChattGPTも参照しているはずですので、東大入試のための特訓を受ける前ぐらいの、ChattGPT4レベルの入試対応能力も一部は継承しているとは思われます。
しかし日経新聞までもが加わった、東大入試に特化した特訓の成果をそのまま引き継いだ01は、R1よりも圧倒的に優位な位置にありましたので、01の持つアドバンテージ抜きにR1と比較するのは、両者の優劣を主テーマとするならば公正さを欠いているといわざるをえません。
東大入試問題をめぐるChattGPT01とDeepSeekR1のバイアスのかかった比較といい、ChattGPTが全記事を作成したイタリアの新聞の紹介記事を横に並列して掲載した記事配置といい、西日本新聞は、報道機関としては許されざる詐術めいた紙面づくりをしていたわけです。孫正義礼賛のために。情けなくなりますね。
のみならず、実際に使うとなるとセキュリティ上の心配があるとはいえ、中国のAI(デジタル)技術は日本をはるかに追い越しているだけではなく、アメリカをも追い越しかねないほどに高度なレベルにあるという事実を、西日本新聞、おそらくは他紙も国民には伝えずに、逆の印象を与えることで、デジタル分野における、日本の致命的な遅れを国民に知らせる機会をもつぶしたわけです。
OpenAIは、DeepSeekがChatGPTの技術を盗んだとして提訴していますが、DeepSeek は、大量データで訓練するというChatGPT(のみならず既存のAI共通)とは全く異なった技術思想で開発されており、この特異点において、DeepSeekは生成AIのブレークスルーを実現したとして世界中の専門家から高い評価を受けています。
AIにその手があったか!DeepSeekの革新性を研究者が論文解説する リープリーパー2025.02.06
(この記事は、保存中にURLが勝手に書き変えられていましたので、念のためURLも書き添えておきます。https://www.leapleaper.jp/2025/02/06/researcher-explains-deepseek-ai-in-papers/
既存の技術を参照しつつもそのまま踏襲せずに、全く新たなアプローチから開発されたDeepSeekは、ChatGPTの10分の一以下の費用で開発された上に、電気消費も非常に少ない高効率で高性能な生成AIを実現しました。
わたしは、この全く新たな視点から生成AIの技術思想が更新されたという事実をもって、DeepSeekはChatGPTを越えたと評価したわけです。
01の急激な性能アップには、OpenAIもDeepSeekの技術思想から多々学んだのではないですか。
驚いたことには、DeepSeekショックで世界中が騒然としている中で、中国を目の敵にしているトランプ大統領は、DeepSeekは使うな!と禁止令を出すのかと思いきや、禁止とは言わずに、アメリカ企業への警鐘になる、参考になるという趣旨の発言をしていたことです。
アメリカ政府としては禁止措置を採っているいるようですが、おそらくイーロンマスク氏が、DeepSeekの特性について説明されたのだろうと思います。DeepSeekに対して、各国首脳の中でこういう発言、評価をしたのはおそらくトランプ大統領だけだと思います。
トランプ大統領は、相互関税という言葉の意味からは完全にかけ離れた、恣意的かつ不当な関税攻勢で自国アメリカをも含めて世界中を混乱に陥れていれていますが、DeepSeekに関しては唯一正確に理解された首脳だと思います。
しかし関税攻勢でアメリカが豊かになるとは思えません。アメリカに限らずどこの国の企業であれ、製品を売るためには品質の良いものを適正な価格で売る努力は必須不可欠です。アメリカ車が日本で売れないのはこの努力が決定的に不足しているからです。EVが売れないのは高価すぎるから。
3.日本のAI敗戦と孫正義
ところで、日本ではAIの活用として最初に話題になったのは、新井紀子氏をプロジェクトリーダーとして2011年に始まり、2016年に事実上中止になった、東ロボプロジェクト(正式名ロボットは東大に入れるか)と銘打たれた東大入試問題へのチャレンジでした。
ライフプロンプトもこの東ロボプロジェクトの流れを受けての起業のようですが、なぜ日本では、AI活用が東大入試問題を解くことが代表選手のようになるのか、不思議でなりません。
実際、東ロボプロジェクトが、日本のAI研究や開発に寄与するような成果を残したのかどうか。それらしきニュースは皆無ですので、成果はほぼゼロだったと思われます。
しかし新井氏は、プロジェクトリーダーとして事業の失敗を糊塗するためか、読解力、読解力と騒ぎながら、日本の教育界をあらぬ方向に誤誘導することに力を注ぎ、AI専門家としての使命を完全に放棄しています。
にもかかわらず、新井紀子氏に対する批判は皆無に近い。以下のわたしの批判ブログは数少ない批判です。未読の方はぜひご覧ください。
10兆円ファンドと新井紀子氏
AIと教育
昨日、以下の東ロボ(新井紀子氏)批判を発見しました。こちらは、AIの専門家による批判です。
東ロボくんは、なぜ失敗したのか 「AI vs. 教科書が読めない子どもたち」批評1ロボ・マインド
以下は、研究者の視点からの批判です。新井氏に敬意を表しつつも、もっとも痛い点をついた批判です。
「東ロボくん」 新井紀子を真っ向から批判する
2018年11月08日 @onionmail123 Qiita
上記批判の肝は、プロジェクトが壁にぶつかった時点で、それを乗り越えようとはせずに、いとも簡単に放棄したという点にあります。これはおそらく誰もが感じているところですが、@onionmail123氏の批判は、同じ研究者の視点からなされているだけに非常に鋭い。
そもそも、研究というのは壁にぶつかってからが本当の始まりである。そして、大半の場合、壁を突破、つまり、課題を解く方法を創り出すことが研究的な貢献であり、論文になる。ただし、その研究分野の最新手法を駆使しても解けない場合、問題提起をすることで研究分野に貢献し、論文にすることもできる。
これを鑑みるに、新井教授は、2016年に限界が見えた時、後者をするべきだったと思う。ところが、あろうことか、日本の高校生の読解力を養う教育がなってないと主張し、社会に問題を提起するという、極めて政治的な方向に進んでしまった。残念ながら、それはもはやAIの研究開発ではない。(「東ロボくん」 新井紀子を真っ向から批判する)
国立情報学研究所の幹部である新井氏は、国家的責務を負ったAI専門家としての矜持はもとより、使命感や義務すらも放棄して読解力推進行脚を騒々しく開始しましたが、その新井氏を礼賛する風潮が日本中を覆い、マスコミを先導役にして、教育界のみならず、経済界をも巻き込んだ狂騒的事態が展開されました。その結果、日本の教育におけるIT/AI・デジタル教育放棄が今日まで続き、デジタル人材の決定的不足を招く結果になっています。
では、東ロボプロジェクトの後継者ともいうべきライフプロンプトは、ついに東大入試突破を実現させましたが、その成功が、同社のAI研究開発を新しいステージへと送り出したのかといえば、素人の身を顧みずにいうならば、東ロボ時代とほとんど変わっていないのではないかというのが、正直な感想です。
東ロボプロジェクトが放棄された2016年に比べると、新たに登場した生成AIが進化し続けましたので東大入試突破は実現しましたが、東大入試突破を実現することで何かを獲得したのか、AIの機能やメカニズムに何か新しい発見があったのかなどは、今のところ伝わってはきていません。
ライフプロンプトはOpenAIに貢献することを意図してプロジェクトを開始したのかどうかは不明ながら、日経新聞の支援まで受けて始まった東大入試プロジェクトは、結果としてChatGPTの性能向上に多大な貢献をしたということだけは、説明なしでも明確に伝わってきます。OpenAIは大喜びだったはず。
つまり、日本における最高の知能の拠点たる、東大に発するAI研究開発の実践が、ChatGPTを使う人の立場からなされただけであったということです。データが増えれば増えるほど性能が高まるというのが初代生成AIの基本原理ですので、広範囲の分野の知識を問う大学入試、東大入試問題への対応力を高める訓練は、良質なデータを使っているだけに、性能アップへの貢献度は他に類を見ないほどであったと思います。なんと日本人はお人好しなのか!
OpenAIからは資金の提供はなかったと思いますので、OpenAIにとってはタダで性能アップに貢献してもらったようなものです。ライフプロンプトにとっては、生成AIへの対応力を強化する機会になったかと思いますが、現状を強化することにはなっても、DeepSeekのようなブレークスルーにつながるような視点は皆無だったのではないか。
また、二代にわたる東大入試突破事業からは、対話型(チャット型)生成AIとは異なった、自律的にタスクを実行するAIである、AIエージェントのようなブレークスルーに繋がる気配も伝わってきません。
中国では、世界初の汎用型AI(AIエージェントのさらなる進化形。人間の指示なしに、人間と同じように自ら自律的に動くAI)までもが登場しています。誕生したばかりですので、どこまで実用に耐えられるのかどうかは不明ですが、あらゆる領域でブレークスルーにチャレンジするという中国人の改革精神は、東大入試突破を大プロジェクトとして推進してきた日本のAI研究にはほとんど無縁に近く、両者の余りの違いに暗澹たる気分に襲われています。
続く中国AIの衝撃、自ら判断するAIエージェント「Manus」がすべてを変える可能性
Craig S. Smith | Contributor Forbes JAPAN 2025.03.11 (恐怖を覚えるほどの高精度な自立型AIエージェント)
創業したばかりのAIベンチャーには酷すぎる批判だと思います。本来は、日本のデジタル研究開発の核となるべき国立情報学研究所の幹部である新井紀子氏への批判とすべきところですが、新井氏が任務放棄していますので、たまたま東大入試プロジェクトに関わった縁でライフプロンプトさんへの批判の形になってしまっています。
そもそも新井氏は、AIは四則計算によって動くだけの機械なので、読解力がゼロであるのは当然。シンギュラリティ(AIが人間の知能を超える技術的特異点)など絶対に起こらないと強く断言していましたので、自律型AIのAIエージェンシーなど考えもしなかったはずです。ましてや、さらに進化した汎用型AIなどありうるとは考えもしなかったはずです。
AI研究者としての任務を放棄した彼女は、子どもたちへのプログラミング教育も否定し、読解力向上事業に力を注いでいます。AI研究者としてのご自身の限界を糊塗するために、日本の教育をゆがめることに力を注いでいるわけです。
そんな日本を尻目に、日本ではほとんど報道されていませんが、中国では人型ロボットでもブレークスルーが次々生まれています。次の記事はAIを搭載した人型ロボット工場ですが、この工場は、ロボットを動かすために必要なデータをゼロから収集するために作られた工場だという。
まるでスターウォーズの世界?「頭脳」訓練工場で黙々と働く、中国の人型ロボットたち
2025年2月14日 36Kr
AI用データを収集するための工場など、日本はもとより、世界でも他に例はないはずです。ましてやAI用データをゼロから収集しようという、ブレークスルーを生み出すようなクリエイティブな発想は、大量データを大前提とした既存の仕組みや権威に依存した、東大入試突破プロジェクトからは生まれようもないはずです。
これはライフプロンプトに対する批判ではなく、事実を伝えない日本のマスコミと、新井氏を含めた日本の専門家と研究の自由を与えない日本政府、歴代政権に対する批判です。
以下は、中国で続々と誕生しているAIロボットのごくごく一部ですが、いずれも、既存の権威的技術を転覆させるほどのクリエイティブな発想で、斬新なAIロボットが猛烈な勢いで生まれています。中国産のデジタル技術や製品はセキュリティ上問題があるとはいえ、危険だといって排斥するだけでは日本の安全は保障されません。
中国、世界初の人型ロボット協働作業を実現 EV工場で実地訓練
2025年3月17日 36Kr(DeepSeekを搭載)
「どこでもDeepSeek」急拡大で各産業を席巻、一方で「AI失業」の問題も―中国
Record China 2025/3/16(あらゆる産業分野で一気にDeepSeekの実装が進む)
「脳」も「体」も造る、進化が加速する上海の人型ロボット産業―中国
Record China 2025/3/15(少ないデータで汎用型AIロボットを開発)
中国では、少ないデータを使ってAIを動かすDeepSeekが一気に広がりを見せる中、大量に作られた巨大なデータセンターが次々閉鎖に追いこまれているという。AIには大量のデータが必要だという常識が覆されたことに加え、いくら優秀でも中国製のデジタル製品を使おうという国が少ない、つまり輸出ができないということが原因のようです。
AIを使った新旧の東大入試チャレンジに対するわたしの批判は、以上のような背景事情を一切隠蔽して、日本国民の現状認識をゆがめてしまうような、西日本新聞をはじめ日本のマスコミに対する批判です。と同時に、孫正義とOpenAIのサム・アルトマン氏の野合に対する批判でもあります。非常に危険です。
孫はトランプ大統領に、75兆円も投資することを約束して、アメリカでスターゲート計画と称するデータセンター建設事業を推進しようとしていいますが、この巨額の資金の調達先はいったいどこなのか。
さらに加えて、日本でもアルトマン氏と組んで6兆円を投じて新会社を設立するという。
ソフトバンクグループ オープンAIと合弁会社設立を発表
2025年2月3日
このニュースは、2か月前のものであることをついさっき知ったばかりで驚いています。わたしは、異形のAIとセック6の追記記事を書いた時点で初めて知ったばかりです。
2か月遅れになりましたが、上記記事を読むと、アルトマン氏は、OpenAIにとって日本はトップ5位に入るほどに大きな市場だと正直に語っています。アルトマン氏は、その大きな日本の市場を独占したいと目論んでいるはずです。
孫はそれを手助けすることで分け前の一部を手にする算段なのでしょうが、この新会社のシェアが拡大すれば、日本のIT企業がAI分野に進出する余地は皆無に近くなるはず。日本企業が関与できても下請け的な立場にならざるをえないはずです。
しかしあきれ果てたことには、石破総理は、日本のAI市場をOpenAIに喜んで献上することにニコニコしながら同意しています。少なくとも先進国では、自国のAI敗戦を進める、これほどの売国的首脳は他に例はないはずです。東大入試突破プロジェクトからも、日本のAI敗戦を阻止する意欲や能力を持った人材など生まれようもないことは明らかです。
日本のAI敗戦で大儲けをするのは、孫正義とアメリカのIT企業のみ。
次回は連載最終回の予定ですが、孫正義の行方についてももう少し詳しく書くことにいたします。